不動産賃貸借契約
契約するなら公正証書で
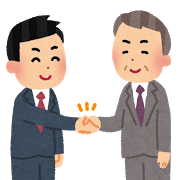
賃貸借契約、金銭消費貸借契約、債務弁済契約など数多くの契約の中には、事業用定期借地権契約や任意後見契約などのように、必ず公正証書によってしなければならないと法律で定められているものがありますが、ほとんどの契約は当事者間だけの口頭や私文書で締結できます。しかし、公正証書によって契約を締結しておくことが最良、最適の方策です。
その主な理由は、次のとおりです。
- 当事者の取り決めに法的に問題がないか、要件等を公証人が慎重に審査します。
- 金銭の支払い債務について、支払いを約束した相手が、その約束を守らず支払ってくれない場合に裁判を起こさずに強制執行できるように手当てできます。
- 公正証書の原本は、契約が効力を生じている間は、公証役場で厳重に保管しますので、万が一手持ちの契約書(正本、謄本)を紛失や毀損しても安心です。
- 証書が真正に成立したものと推定され、当事者が記載事項を陳述したことも証明され、万一紛争が生じ、裁判となっても有力な証拠となります。
たとえば、不動産の賃貸借契約の場合、公正証書で契約を締結しておけば、貸主側(賃貸人)は、もし借主(賃借人)が賃料等を支払ってくれなければ強制執行することができます。借主側(賃借人)も、貸主(賃貸人)に敷金や保証金など返還を予定しているお金を預けているのに返してもらえない場合、強制執行できます。手持ちの証書を紛失しても公証役場で再発行できます。将来不幸にも紛争が生じたときも、強い証拠として証書を利用できます。さらに、記載すべき法律事項等に無効となるものや問題がないかについても公証人が入念にチェックしますので安心です。重要な契約は公正証書により締結することを強くお勧めします。
賃貸借契約について
賃貸借契約は、当事者の一方が金銭等の対価(賃料)を支払い、他人の物を使用、収益することを目的とする契約です。目的となる物は、動産でも不動産でも構いませんが、社会的機能から見て不動産の賃貸借が重要であり、法の規制も民法だけでなく借地借家法など特別法による修正が加えられています。
借地借家法は、借地権(建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃貸借)の存続期間、効力等及び建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続きに関し必要な事項を定める法律です(同法1条)。
- <民法の原則(民法604条)>
-
期間を定める場合、存続期間は50年を超えることができません。契約で50年より長い期間を定めたとしても50年に短縮されます。また、期間は更新することができますが、その期間は更新のときから50年を超えることができません。
期間を定めない場合、いつでも解約の申入れ可能。解約申入れすれば、土地は1年、建物は3か月で終了します。
- <不動産賃貸借の種類>
-
- 建物所有を目的とする土地の賃貸借
存続期間 更新 建物買取請求権 通常借地権 30年(契約で30年以上も可)(合意により短くできない。期間が定められていない場合には30年とされる) 強制更新あり
初度更新20年
以後更新10年
(合意により長期にできる)あり
(放棄特約は無効)事業用定期借地権 10年以上30年未満の一定期間 なし なし 30年以上50年未満の一定期間 特約で排除 特約で排除 定期借地権 50年以上の一定期間 特約で排除 特約で排除 一時使用目的の借地権 一時使用目的のために借地権を設定したことが明らかな場合で短期間を想定 特約で排除 特約で排除 建物譲渡特約付き借地権 30年以上で「相当の対価」による建物譲渡特約の効力発生の時まで - 建物の賃貸借
存続期間 法定更新 造作買取請求権 普通建物賃貸借 期間を定めることも、定めないこともできるが、期間を定めるときは1年以上の期間(1年未満の期間を定めても期間の定めのないものとみなされる)期間の定めのない場合、賃借人は、3か月の猶予期間をおいていつでも解約申入れできるが、賃貸人は、正当事由がある場合のみ、6か月の猶予期間をおいて解約申入れができる あり
更新後の期間は定めなきものとみなされる特約で排除できる 定期建物賃貸借 当事者の定めた期間(1年未満でも可) 特約で排除前提 特約で排除前提 取壊し予定建物の賃貸借 法令・契約により建物を取り壊すこととなる時まで(期間を定めることも、定めないことも可) 特約で排除前提 特約で排除前提 一時使用目的の建物賃貸借 一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借であり、設定目的達成までの比較的短期間を想定 特約で排除前提 特約で排除前提
- 建物所有を目的とする土地の賃貸借
事業用定期借地権契約とは
事業用定期借地権は、借地借家法の改正(平成19年法律第132号)によって認められるようになった
- 契約の更新がなく
- 建物の再築による存続期間の延長がなく
- 建物の買取請求権のない
借地権です。借地借家法23条に規定されています。この借地権は、専ら事業用の建物を所有するための借地権に限られます(居住用の目的の建物は除かれます。)。なお、賃借人自身が建物において事業を営まない場合でも賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に借地権を譲渡・転貸し、その第三者が事業用に供する建物を建築して所有することでもいいとされています。
存続期間の長短により次の2種類があります。
- 存続期間が30年以上50年未満の借地権の場合。貸主と借主が、契約の更新及び建物の再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないことを約束すると、更新などのない借地権になります(借地借家法23条1項)。
- 存続期間が10年以上30年未満の借地権の場合。法定更新、建物の再築による存続期間の延長及び建物の買取請求権に関する法の規定は、適用されません(借地借家法23条2項)。
事業用定期借地権は、公正証書によって締結しなければなりません(借地借家法23条3項)。これは法の要請であり、公証人に要件を慎重に審査させ、脱法的乱用が生じないようにしているのです。

期間満了時に更新できる旨の定めは、この事業用定期借地権の本質に反することから認められません。ただし、期間満了時に一旦賃貸借が終了した上で、新たな借地権設定契約ができる旨当事者間で合意すること自体はそれが脱法行為とみなされない限り有効です。また、事業用定期借地権の法定期間内であれば、延長することは可能と考えられます。
定期借地権契約とは
存続期間50年以上の借地権(借地借家法上、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を借地権といいます。)については
- 期間が満了したときに契約の更新がないこと
- 建物の再築による存続期間の延長がないこと
- 建物の買取請求をしないこと
の特約をすることができ、期間が満了すれば契約は終了し、土地は更地で戻ってきます(借地借家法22条)。
この特約は公正証書による等書面によってすることとされており、公正証書によることをお勧めします。
定期建物賃貸借契約とは
建物の賃貸借契約で、当事者の自由な合意によって選んだ契約期間(例えば6か月、1年、3年等)を経過すれば必ず当該建物の賃貸借を終了することができます。これが定期建物賃貸借契約です。建物の賃貸借契約について適用のある借地借家法38条に規定されています。また、同法39条の取壊し予定の建物の賃貸借や、同法40条の一時使用目的の建物の賃貸借では、「本契約は、期間満了により終了するものとし、更新することができない。」との約定を入れることができます。
定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、更新排除特約の効力が認められます(借地借家法38条1項前段)。公正証書によることをお勧めします。

建物の賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、「当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了すること」につき、その旨を記載した書面を交付して説明することが必要です(法38条2項)。この説明がなければ更新排除特約は無効となります(同条3項)。
不動産賃貸借契約における特約
本来、私法上の契約は、契約自由の原則が適用され、その方式や内容については当事者が自由に定めることができるのが基本ですが、不動産賃貸借、とりわけ居住用の土地・建物の賃貸借については、借地人や借家人の保護の見地から契約自由の原則が修正されています。この種の契約では、やはり貸主側の方が借主側よりも強い立場にあるため借主側に過度の義務負担を強いる傾向がみられます。そのことから契約時の特約も後々トラブルの元になりかねず、裁判で争われて結局無効とされることもあるので慎重な検討と配慮が必要です。
注意を要するポイントは次のとおりです。
- 賃借人に義務を負わせる特約が、決して暴利的と言えない合理的、客観的な理由があること、及びそれを賃借人が理解し、自由な意思に基づいて明確に同意したと認められるものであること
- 特約の内容が公の秩序、又は善良な風俗に反するものでないこと
- 借地借家法は、借主の保護を図っている片面的強行規定が多く設けられており、特約がそれに反して借主に不利な内容でないこと(借地借家法9条、16条、21条、30条、37条)
- 特約の当事者が「事業者」(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人)と「消費者」(事業者としての立場でない個人)の関係にある場合には、両者は情報の質や量、又は交渉力に大きな差があることから消費者契約法の適用があるので、同法に反する内容でないこと
たとえば、
- 事業者の損害賠償責任を免除する特約は無効とされる場合があります(消費者契約法8条)。
- 契約解除に伴う損害賠償を予定し、又は違約金を定めている場合は、その合算額が平均的損害額を超える部分は無効とされ、遅延損害金についても年14.6パーセントを超える部分は無効とされます(同法9条)。
- 消費者の権利を制限し、又は、その義務を加重する条項で信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する特約は無効とされます(同法10条)。
賃貸借ちょっと相談室(Q&Aのコーナー)
期間の定めのある借家や借地の賃貸借の賃借人は、期間の途中で解約申入れができますか?
まず借家の場合ですが、その賃貸借契約には中途解約条項(契約期間中であっても当事者の解約申入れによって解約申し入れできる旨の条項)があれば、その条項に従って解約の申入れができます。中途解約条項がなければ、原則として解約申し入れはできません。
ただ、その賃貸借契約が居住用建物(建物床面積が200㎡未満の場合)の定期建物賃貸借契約の場合なら、賃借人の転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない場合事情で賃借人がその建物を自己の生活の本拠として使うことが困難になったときは解約の申入れができ、申入れの日から1か月を経過すれば終了します(借地借家法38条5項)。 なお、賃貸借契約が定期建物賃貸借契約でなかった場合ですが、その場合でも賃借人の側に賃貸借契約時に予測困難な事情の変化が生じて賃貸借契約を継続することが困難となったときは事情変更の原則により解約できる場合もないとはいえません。
次に借地の場合ですが、中途解約条項がある場合は、解約申入れができます。中途解約条項がない場合は、原則として解約申入れができません。ただし、賃借人の予測困難な事情の変化が生じて賃貸借契約を継続することが困難となったときは事情変更の原則により解約できる場合もあると考えられます。
それでは、期間の定めのある賃貸借の賃貸人は、期間途中で解約申入れができますか?
その契約に中途解約条項があって、その条項によると、賃貸人に解約申し入れに当たって正当な事由が必要であるとし、解約申入期間を6か月以上設けているなど賃借人の保護が図られており同条項が無効と考えられない限り、中途解約条項に従って解約申し入れができると考えられます。 中途解約条項がない場合は、賃貸人は解約申入れができないと考えられます。
期間の定めのない建物賃貸借の賃借人は、いつでも解約申入れができますか?賃貸人からはどうですか?
はい、賃借人は、いつでも解約申入れができます。解約申入れした場合は、その日から3か月の期間が経過すれば賃貸借は終了します(民法617条1項2号)。
次に、賃貸人は、正当な事由がある場合に限って6か月間の明渡猶予期間をおいて解約申入れができます(借地借家法27条1項、28条)。
まとめ!中途解約について
- 期間の定めのある借地権(普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権等)
賃借人からの解約申入れ 賃貸人からの解約申入れ 中途解約条項有 可 不可
借地権者に不利な特約は無効(借地借家法9条、16条、21条)中途解約条項無 原則不可
ただし契約時に予測困難な事情変更の生じた場合に認められることあり不可 - 期間の定めのある建物賃貸借
賃借人からの解約申入れ 賃貸人からの解約申入れ 普通建物賃貸借(中途解約条項有) 可 正当事由があり、解約申入期間が6か月以上ある場合は可能と考えられる。 普通建物賃貸借(中途解約条項無) 原則不可
ただし契約時に予測困難な事情変更の生じた場合に認められることあり不可 定期建物賃貸借(中途解約条項有) 可 正当事由があり、解約申入期間が6か月以上ある場合は可能と考えられる。 定期建物賃貸借(中途解約条項無) 原則不可
ただし、居住用建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合は当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に限る。)で、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、解約の申入れをすることができ、解約の申入れ日から1か月を経過することで終了する。不可
賃貸人が解約の申入れをする際や更新を拒絶して借地や建物の賃借人に退去してもらう場合に必要とされる正当事由とはどのようなものですか?
まず、土地の賃貸借ですが、借地権設定者による更新を拒絶するための正当事由については、借地借家法6条で、①借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情、②借地に関する従前の経過、③土地の利用状況、④借地権設定者が土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して判定すべきことと定められています。
次に、建物賃貸借の場合ですが、更新拒絶の正当事由の判定は、借地借家法28条により、①建物の賃貸人及び賃借人 (転借人を含む) が建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況⑤建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮すると規定されています。 これらは、自由な解約権を認めている民法の規定を修正して、賃貸人の私利私欲を制限して、借家関係の適正な継続を図るために設けられているのです。
公正証書で不動産賃貸借契約書を作成した場合、賃借人が約束を守らない場合に裁判を起こさなくても強制執行できると聞きましたが、立退いてくれない賃借人を強制執行で立退かせることもできるのですか?
それはできません。公正証書中に「強制執行認諾条項」(債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服するとの陳述)が記載されていると裁判手続き等を経ずに強制執行できることになりますが、公正証書で強制執行できるのは、あくまでも金銭支払請求権や代替物の給付請求権に限られ、たとえば、不動産の明渡し、動産の引渡し、意思表示等については強制執行できる旨の公正証書を作成することはできません。